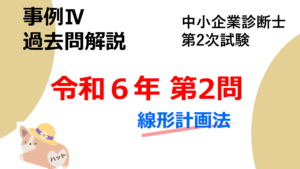【2次直前期】「型」の確立(確認)と本番シミュレーション
いよいよ10月26日(日)に行われる中小企業診断士2次試験(筆記試験)が近づいてきました。
受験される皆様におかれましては、最終段階の仕上げ時期に入っていると思われます。
既にYoutubeやブログ等(SNS)で、診断士2次試験直前期に関する様々な情報が発信されていますが、事例Ⅳに関連して2点申し上げたいと思います。
1.型を確立(確認)する
事例Ⅳに限りませんが、解答の型の確立(確認)を意識したトレーニングが必要な時期と思います。
「型」とは、本試験において80分という制限時間内で合格点に到達するための自分なりの解答手順です。
例えば、事例ⅣのNPV(正味現在価値)を例にとると、問題文の図解や計算用紙(余白部分)の使い方、解答欄(計算過程)への記入方法といった細かい点も含みます。また、問題を解く上で必要な情報を過不足なく拾い上げるための意識も大切になります。
例えば、NPVの問題では、
(1) 各年度に共通するキャッシュフローの計算
(2) 年度特有のキャッシュフローの計算
を意識することも大切です。
(1)については、「年金現価係数」で一括割戻しが可能ですが、(2)は(基本的に)個別に複利現価係数で割り戻すことになります。
(2)の代表格は、❶運転資本の増減(プロジェクト終了後の運転資本の戻りを忘れずに)、❷(新設備導入に伴う)旧設備の売却です。
特に、❷については、ⅰ)売却収入に係るキャッシュフローが期首(=新設備導入時)に生じるのに対して、ⅱ)売却損に係る税効果が期末に生じるというタイミングのズレに注意することが大切です。
事例Ⅳの設問文はかなり長く、(問題を解く上で)余分な情報が散りばめられていることもあるので、ともすると問題文に翻弄(圧倒)されがちです。この点、予めNPVの論点をしっかり押さえておくことで、問題文を読みながら必要な情報を漏れなく拾ってくることができます。
パズルの完成図が頭にあれば、パスル完成に必要なピースを短時間に集めることができるわけです。
2.本番シミュレーション
2次試験は「80分 × 4科目」のハードな試験です。(私も経験しましたが)試験終了後の疲労感は1次試験とは比べ物になりません。
特に、最終科目の事例Ⅳには相当疲労が蓄積された状態で取り組むことになります。
予備校等で模擬試験を受けられた方は恐らく体感できているでしょうが、(模擬試験を受験する)時間的な余裕がなかった方は、一度、(1日の勉強終了直前の)疲れた状態で、事例Ⅳの問題を解いてみることを勧めします。
また、疲労回復の対策も重要と思います。休憩時間の体操、疲労回復サプリなど。
ただ、「本試験当日にいきなり…」ではなく、今のうちから色々試してみて効果ありそうなものを本試験当日に行う(使用する)というのが良いと思います。
特に、「本番シミュレーション」は、私が受験した際には意識が薄かったため、本試験では結構失敗してしまった感がありました。
皆様方の合格を祈念いたします。