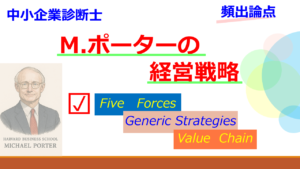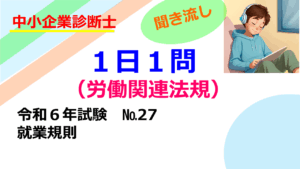【中小企業診断士試験】令和8年度から口述試験廃止へ
中小企業経営支援分科会(第41回)(書面審議)の資料2‐2によると、中小企業診断士試験の受験手数料の見直しを行う中で、令和8年度から口述試験が廃止されるようです。よって、令和7年度(令和8年1月25日実施予定)の口述試験が最後となります。
口述試験の廃止理由は、(中小企業診断士一次試験・二次試験を通じた)人件費や会場費の高騰といった経常的経費の増加により、 日本中小企業診断士協会連合会の財政状況が悪化し、安定的な試験事務の実施が困難となる可能性があるため、ということです。
口述試験を廃止しつつ、(他の国家資格の受験料との比較してやや高額な)現在の第一次試験と第二次試験の合計試験料(32,300円)は維持される方向性とのことです。
本資料では、口述試験の廃止に至った理由が挙げられています。
❶ 口述試験は、第二次試験筆記試験合格者を対象に助言スキル(コンサルティングスキル)を試験するものとして平成13年度から実施。2名の面接官による10分程度の面接形式で行われるが、過去10年間で不合格となった受験者(当日欠席者を除く)は3名のみ(合格率99.98%)であり、適性試験として十分に機能しているとは言えない。
❷ 他方、中小企業診断士の登録については、第二次試験合格後の中小企業に対する診断助言業務への従事又は登録実務補修機関が行う実務補修の受講が要件となっており、これらを通じて、中小企業診断士に求められる助言スキルの向上が可能であることから、第二次試験筆記試験合格者を対象に口述試験を行う実益は乏しい。
以上を踏まえ、受験者の試験への負担軽減、日診連における経費削減及び試験プロセスの効率化の観点から、口述試験の廃止による第二次試験の受験手数料の引下げを検討する、ということのようです。
なお、「中小企業診断士試験に関する検討委員会とりまとめ」には、口述試験に関する更に詳しい事情が記載されています。
以下は引用です。
2.検討に当たって考慮した事項(口述試験の廃止)
中小企業診断士試験は、多肢選択式の第1次試験および、筆記試験と口述試験からなる第2次試験で構成されている。
口述試験は、平成13年度の試験の法定時、中小企業診断士を、民間経営コンサルタントとして位置付け、その役割を「診断」から「診断及び助言」へと充実させたことを背景に、中小企業の診断及び助言に関する実務の事例並びに助言に関する能力について口述の方法により確認するものとして導入された。 筆記試験と口述試験は一体的に第2次試験として位置付けられ、筆記試験で一定基準以上の得点を得た者のみを対象に実施されているが、受験手数料は筆記試験と口述試験を合わせて第2次試験手数料として徴収している。 平成24年度の受験手数料改定時でも口述試験は検討の俎上に上り、面接員を3名から2名とする経費削減策が提案された他、筆記試験と口述試験の受験手数料を分割することも検討された。面接員の縮減は実施したが、受験手数料の分割はかえって手数料の増額となるため見送られた。「口述試験は、例年1月下旬、筆記試験と同じ全国7地区で行われている。1名の受験者に対し2名の面接員が、筆記試験で出題した4事例などにもとづいて質問し、受験者は中小企業診断士の立場に立って回答(診断、助言)する。所要10分程度と短時間ではあるが、受験者にとっては移動時間や宿泊・交通費など一定の負担が生じている。 口述試験の受験者数は、第1次試験受験者数の増に伴い、増加傾向にあり、直近5年の平均で約1,400人である。第1次試験や筆記試験に比べれば人数こそ少ないが、問題作成、試験会場の確保、試験会場運営、これらに付随する管理業務など、他の試験同様の作業、相応の経費を要している。 口述試験の合格率は、累計99.9%であり、また、中小企業診断士は資格登録までに、試験の他、「実務従事・実務補習」または「養成課程等」が課せられているため、当初の目的である「診断に加えた助言能力の獲得」の機会は制度全体を通じて確保できていると言え、口述試験を廃止することにより、試験の簡素化、受験者負担の軽減、受験手数料の適正化を図ることができる。
出所:「中小企業診断士試験に関する検討委員会とりまとめ」 令和7年2月 一般社団法人 日本中小企業診断士協会連合会
個人的には、妥当な見直しだと思いました。